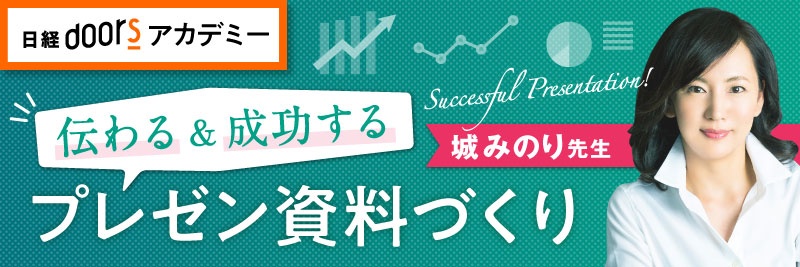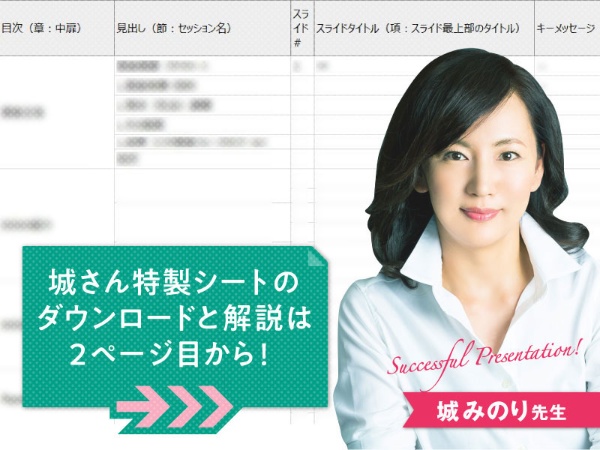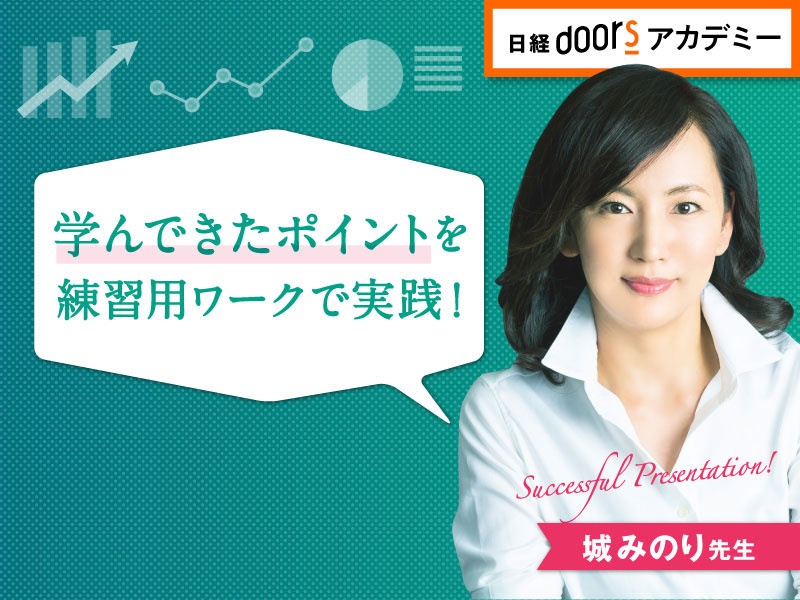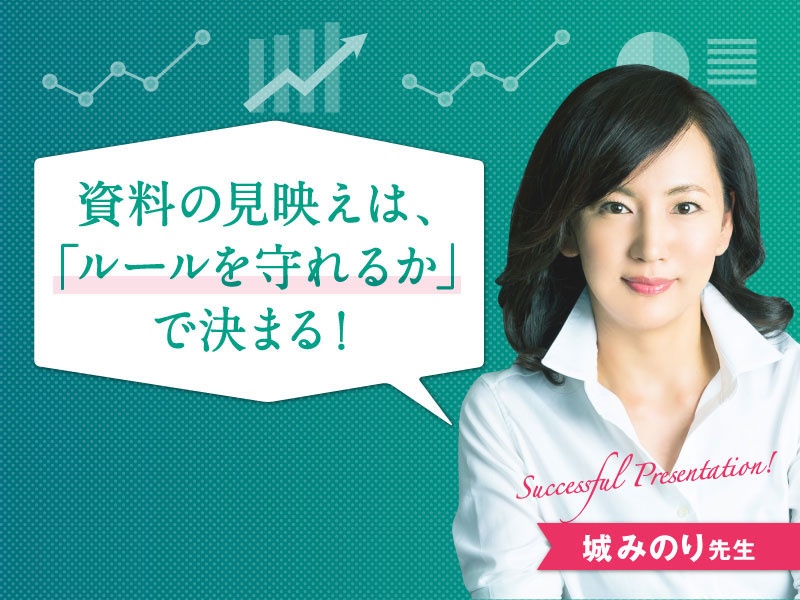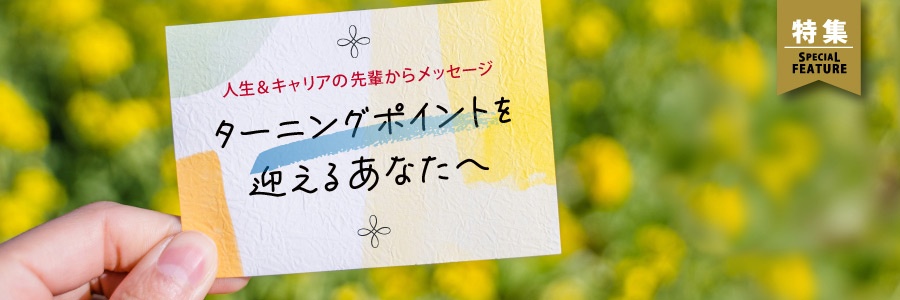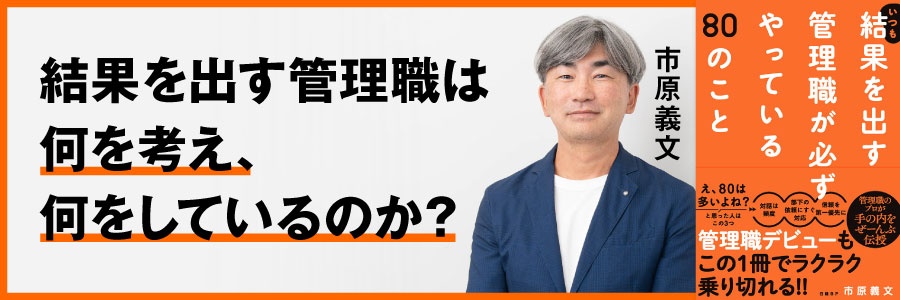ビジネスシーンで今すぐ役立つノウハウをお届けする「doorsアカデミー」のプレゼン資料編、第2回は資料の「屋台骨」となる構成のしかたを学びます。
プレゼンの「ストーリー」、独り善がりになってない?
こんにちは。グローバル・カルテット代表の城みのりです。皆さんはプレゼン資料を作るとき、「ストーリー(ロジック構成)」を意識したことがありますか?
リアルの講座を開催する機会などで受講者に尋ねると、自分では「意識できている」と思っている人が多いです。クライアントなどプレゼン相手に、どうしたら提案内容を理解してもらえるのか――。確かに、一番気を使うのは「ロジカルな説明」なので、そういう自己認識が強くなるのかもしれませんね。
ただ、「ストーリーには気を配っている」という声と同時に、こんな証言も聞こえてきます。
「実は、部署で引き継がれる資料を焼き直したり、継ぎはぎしたりして使っている」
「長めの資料になると、どういう順番で要素を並べたら効果的なのかに悩んでしまう。ページを入れ替えるなどの作業に時間が掛かる」
残念ながら、これらに心当たりのある人は、意識しているはずの「ストーリー」が独り善がりのものになっている可能性が高いです。プレゼンのストーリーには鉄板の構成があり、それが身に付いているなら迷う必要はないからです。2ページ目から、相手に伝わる構成とはどういうものなのか、学んでいきましょう。パワーポイントは使いません。