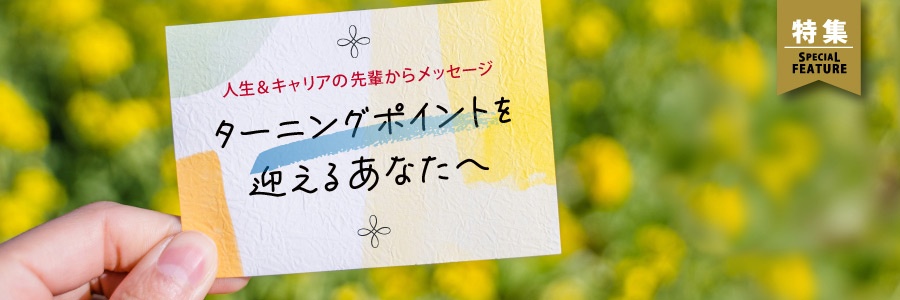インターン中に組織体制の刷新を提案
松永さんがユニークな働き方や取り組みを始めたのは、大学時代。当時の松永さんは、自分の得意分野を見つけられず悩んでいた。
「もともと勉強がとっても苦手で。都内の農業系高校に進学した頃は声優を目指していました。でも、声優の仕事をやり通す自信を持ち続けることができませんでした。自分の表現力で食べていける気がしなかったんですよね。ですので、今度は表現をマネジメントできる仕事に就こうと思って、頑張って大正大学の表現学部・表現文化学科・エンターテインメントビジネスコースに進学したんです」
大学ではイベントをゼロから作り上げる方法を学んだ。例えば、学外のNPOから借りた自然映像を上映する「映像祭」イベントでは、4人いる統括の1人としてクラスをまとめ、100人ものお客様を集めるなど、成功体験も積んだ。それでもまだ「自分には何もできない」という思いがどうしても拭いきれなかった。キャップクラウドのインターンに参加したのは、そんな大学3年の7月のことだ。
最初は顧客情報の入力などの事務作業を任された。「それまで学校で自分のオリジナリティを表現する訓練ばかりしていたこともあったのか、決まったルールに従って業務をこなしていくのが性に合わず、うまくできなくてへこみました」
自分にできることは本当に何もないのか――。悩みながらインターンを3カ月ぐらい続けたころ。社内の組織体制が確立されていないという課題が見えてきた。そこで松永さんは「社員を横や縦の軸で組織化して業務効率を上げたい」と、組織体制の刷新を社長の萱沼徹さんに提案。それが採用されたことを皮切りに、リモートワーク制度やバースデー休暇制度、永年勤続表彰制度、年1度の社員参加型イベントなどの制度を整えるまでになった。くすぶっていた松永さんがやっと活躍の場を見いだした瞬間だった。
萱沼さんは当時の松永さんをこう振り返る。「会社の15周年パーティーを松永に任せたことがあるんです。国立科学博物館でケータリングした料理を提供するというイベントを、社会人の大先輩とともに運営し、見事実現。ゲストの皆が喜ぶ記憶に残るイベントに仕立ててくれました。インターンの後も、この会社にその感性や感覚を吹き込んでほしいと思いました」
今や松永さんと萱沼さんは、数多くの議論を重ねるような間柄に。本気で言い合うこともある。これもすべて「私」という人間を存分に活用してもらうため。「そのためには私ができるだけシンプルで分かりやすい存在でいたほうがいい。だから、感じたことは率直に伝えるようにしています」と言い切った。
仕事は嫌なものだと思っていた
「この会社で働くまでは、仕事って嫌なものだと思っていたんです。でも働くうちに楽しくなってきて。今は仕事とは自分の得意なことを社会に還元できる窓口であると感じられるようになってきました。自分の得意なことが誰かの役に立てれば、幸せだなと思って、日々仕事に取り組んでいます。」
他社に就職した同期の中には、仕事でやりがいを見つけることができずに辞めてしまう友達もいる。
「会社が求めていることと、自分の得意なことは必ずしも常に一致するわけではないと思っています。だからこそ、自社で自分の得意なことを発揮できる瞬間があるとすごく嬉しいんですよね。その瞬間に出合うためには、自分の会社での役割と自分の得意なことをすり合わせていくことが必要だと思うので、学生時代に必死に自分の価値を探すことによって社会人になる練習ができたことは、すごく貴重な時間であったと感じています」
今なら分かる。「何もできない」という大学生のときの焦燥感こそが、今いる場所に自分を導いてくれたことを。
取材・文/小田舞子(日経doors編集部) 写真/稲垣純也