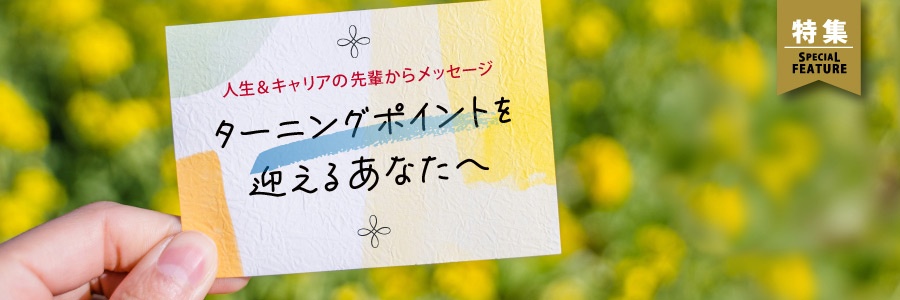自社サービスがうまくいかない状況下で、既存投資家からの300万円の追加出資が決まった。それもすぐに尽きることが目に見えている中、私は打開策を探っていた。
※【第13話】「既存投資家からの追加調達」
渋谷の道玄坂のラブホテル街にある小さな焼鳥屋。網に並べられた串がパチパチと音を立てる。
私はそのカウンター席に座っていて、隣には加賀美がいた。「久しぶりに会おうよ」と彼から連絡があったのだ。松原も一緒に来るはずだったのに、子どもが熱を出したからと言って直前で帰ってしまった(松原はあの性格で、なんと結婚していて2歳の子どもまでいるのだった)。
福岡以来、私と加賀美はまた2人きりになってしまった。しかし今日はなんとしてでも、加賀美の仕事モードを引き出して、真剣なアドバイスをもらいたいと意気込んでいた。今の会社の状況――アプリは落ち目で、調達資金は尽きかけていて、つなぎの300万円はすぐに終わってしまいそう――に対し、加賀美ならどうするかを聞きたかった。
私は自分のコミュニケーション能力(仲良くなる能力ではなく、相手から必要な情報を聞き出す能力)を試すような気持ちでいた。焼き鳥は香ばしくておいしかったが、こんな場所にある店に連れてこられて、このあとの相手の目的も明確な気がして、早くも自信を失っていた。加賀美はさっきから、一緒に飲んだことのある女優の名前を列挙していた。
カウンターだけの小さな店で、寡黙な店主のおじいさんにも加賀美の話はすべて聞こえているはずだ。しかしおじいさんは完全な無表情を維持している。ラブホテル街の老舗となると、客のあらゆる話を、こうして一方的に聞かされ続けてきたはずだ。私は「このおじいさんと飲みたい。彼の話を一方的にずっと聞いていたい」と思った。加賀美には、「そうなんですか」「すごいですねえ」などと相づちを打ちながら、タイミングを見計らっていた。
「あの子ね、最近よくCMに出てるけど、不倫してるらしいよ。前飲んだときに……」
「質問があります!」
話の切り出し方が分からなくなり、ついに私は突然言った。加賀美はびっくりして日本酒を少しこぼした。「……突然すみません、加賀美さんならこの気持ち、分かってくれると思うのですが、実は会社の状況がまずいんです。だからそのことでずっと悩んでいて、それが解決されないと、他の感情を動かすことができそうにありません」
「本当に君っておもしろいね」と加賀美は言った。「先輩に話してごらん」
私は会社の状況を説明した。加賀美はじっと聞きながら日本酒を飲んでいた。今日は眼鏡の色とよく合う、薄いブルーのパーカーを着ている。
「加賀美さんならどうしますか?」
話し終わって質問すると、加賀美は「同じのをもう1杯」と店主に言った。そして黙ったまま斜め上を向いて、柔らかそうな髪の毛を細い指で巻くように触った。いつもヘラヘラと笑っている加賀美がそうやって真顔になると途端に目つきが鋭くなり、さっきまで芸能人の自慢話をしていた人間とは別人みたいに見えた。
「バイラルマーケティング(※)施策」と加賀美は言った。
新しい日本酒が出され、私はそれを加賀美のお猪口(おちょこ)に注いだ。
「俺だったら、今の状況で頭を下げて投資家を回ることは一旦やめにする。消耗するし、条件もどんどん悪くなって、その後の調達にも響いてくるから。資本政策は基本、不可逆だからね。
それよりサービスを伸ばすことに注力して、投資したい会社になるのが一番いいでしょ?
そのためにどうするかというと、バイラル施策を打つべきだと思う。何らかのトリガーをつくって、ユーザーがサービスをシェアしてくれる導線を設計する。バイラル係数(※)が伸びていけば、広告を打つお金がなくても良い数字が出る。そんなことができるなら誰だってやりたいと思うけど、まあ多分、君ならできるんじゃないかな」
「バイラル施策。マッチングサービスの『使っていることを他人にあまり言いたくない』という性質上、最初から無理なものと諦めていましたが、確かに、今の状況でバイラル係数を伸ばせたら調達は格段に有利になりますね」
「何も、サービス自体をバイラルさせなくてもいい。それ用の機能やページを別途作って流行らせて、そこから流入させる手もある。バイラル施策は他人の気持ちが分かる人じゃないと設計できないから、君なら向いているんじゃないかと思うんだ。ほら君って、優しいから」
加賀美は私の手に触れた。彼の仕事モードはほんの数分しか続かなかったが、それでも有益な話を聞けたことが嬉しかった。
「アドバイス、本当にありがとうございます」
「ほらまたそうやって、俺と距離を取ろうとしてる。ねえ敬語使うの、やめてよ。もっと仲良くしゃべろうよ」
「私、年上の人が好きなんです。自分だけ敬語で話していると相手が年上だって実感できるので、このままがいいですね」
「そういうことなら、ぜひそうしよう」
私はビジネスモードとそうじゃないモードを自分の中で調節して、つまらないやつになりすぎないようバランスを取った。
その店を出ると、案の定、加賀美はラブホテルを指さして「ちょっと休憩していこう」と言った。私が「そういうわけにはいきませんよ」と渋ったので我々はすぐ近くにあるバーに入った。
加賀美はウイスキーをロックで立て続けに2杯飲んだ。今日は私より酔っているように見えた。酔うと頬が赤くなり、目が潤んだ。加賀美はよくある酔うほど陽気で冗舌になるタイプとは逆で、一定ラインを越えたあたりから、口数がどんどん少なくなっていった。それに伴って彼は次第に魅力的になった。
「実は俺も、会社がヤバいかもしれない」。加賀美がぽつりと言った。
「え? どういうことですか? 資金なら腐るほどあるじゃないですか」
「ちょっともうだめかもしれないな」
「何かあったんですか?」
「そもそも俺がだめかもしれない」
加賀美が両手で頭を抱えるようにしてそんなことを言うので、私は店員に水を2つ頼み、両方とも彼に飲ませた。
「そんなことないですよ、加賀美さんは成功していて、我々若手の尊敬の的なんですから」
「そんなのなんの意味もないよ。君も同じ立場になれば分かる」
「なってみたいものですね」
「今日は寂しい。1人だと眠れないよ。一緒にいてよ」。加賀美はかすれた小さな声で言った。薄い背中が弱々しく見えた。そのとき、加賀美が「ああそうだ」と言ってポケットから何かを取り出してカウンターに置いた。コトリと音がした。それは福岡で置き忘れた青い蝶(ちょう)のピアスだった。
「これ、忘れてたやつ」
ピアスを手に取った。それは別れた彼氏がくれたものだった。そのことで感傷的な気持ちにならない自分に、私は傷ついた。
一緒にいようよと言い続ける加賀美を振り払うようにしてタクシーに乗った。深夜の空気が少し開けた窓から吹き込み、ここが渋谷だとは思えないほど、清浄な香りがした。彼はあれからどう過ごすのだろう。自宅の六本木ヒルズに帰って、1人で眠るのだろうか。「ちゃんと水を飲んでくれるだろうか」と少し心配になり、《今日は本当にありがとうございました。大事なアドバイスもいただけて助かりました。少し飲みすぎていたようだったので、お水をたくさん取ってくださいね》とメッセージを送った。それからすぐに返信が届いた。
《今日は遅くまで付き合わせてごめんね。一緒に過ごしてくれてありがとう。水飲みます、心配してくれてありがとう》。普段の加賀美らしくない文面だ。
私は窓の外で流れる夜景を見ながら、澤田さんのことを考えていた。今、眠っているのだろうか。どんな夢を見ているのだろう。
そして自分の部屋ではなく、オフィスの前でタクシーを降りた。
午前3時、誰もいない真っ暗なオフィスに入ると、ひんやりと空気が冷たい。一部の電気をつけて、自分のデスクに座る。さっき飲んだウイスキーのせいで頭が痛くなりはじめていたので、今週3度目の頭痛薬を飲んだ。
私はため息をつき、少し迷ってから、ピアスを耳につけた。
絶対に結果を出さなければいけない。
写真に書かれた「死ね」の文字が脳裏に浮かぶ。ここで成功できなかったら私には居場所が、存在価値がなくなってしまう。
切迫した気持ちでコピー用紙にアプリの画面を描いていき、どこかにバイラルさせるポイントがないか検討した。そしてこのアプリのコアコンセプトである内面マッチングを体現できるようなサイトはどんなものかと考えた。
窓の外が白んでまぶしい光が差し込んだとき、私は傷んだ野生動物が食糧を守るようにして、背中を丸めてひたすら紙に向き合っていた。ここで挽回できるかどうかに、人生すべてがかかっているような気持ちだった。そんな考え方は間違っていると頭では理解していても、心はもう、成功した自分以外、許すことができなくなっていた。ふと顔をあげると前の壁で青い光がちらちらと動いていた。それは私の蝶のピアスに反射した太陽光だった。
※バイラル係数:サービスの拡散度合いを測定する指標。 既存ユーザー経由で獲得した新規ユーザー数で表される。
文/関口 舞