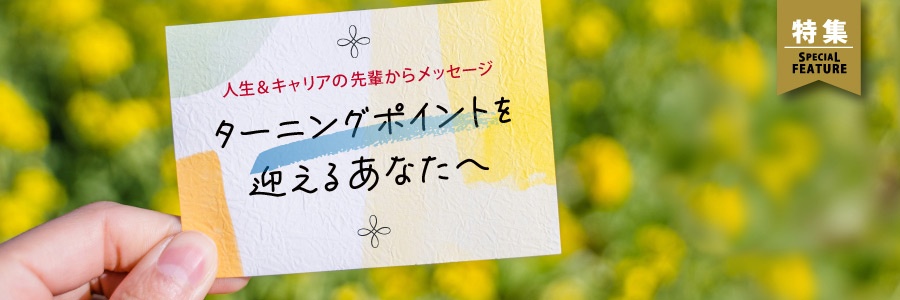松原が福岡で出会ったという外資コンサル出身起業家の神崎透は、高齢者向けサービスのベンチャーを経営していて、既に1億円を資金調達している。我々にも資金調達のアドバイスをくれるなど、起業家仲間として付き合いがあった(※参照:【第11話】「2度目の資金調達」)。しかし以前、彼が私たちに紹介してくれたエンジェル投資家の渡辺さんが、神崎と連絡がつかないと困っていた。
※【第15話】「渾身の企画とサイコパス」
渡辺さんから連絡があり、明日、投資家陣4名で神崎のオフィスに行くことになったと告げられた。もっと早く訪問したかったが、登記されている住所はバーチャルオフィスで存在せず、実際の事務所の場所も度々引っ越しをした形跡があって突き止めるのに時間がかかったという。心配と好奇心で、我々もなんとなく同行する流れとなった。「突撃訪問なんてわくわくしちゃう」と松原は不謹慎なことを言った。
神崎の事務所は五反田駅から15分程歩いたところにあった。中華系のマッサージ店がいくつか営業している雑居ビルの3階で、エレベーターが小さすぎるので我々は階段で上がった。途中でアロマオイルのような、酸化した油の匂いがした。
小さな扉に会社名が印刷されたシールが貼られている。朝から焦りを帯びたイラつきを見せていた投資会社社員の吉岡さんは、インターフォンを押さずに勢いよくドアを開けた。
そこにはいくつかのデスクとPCが置かれていて、2名の社員がいた。彼らはどちらも30歳前後の男で、私たちを見て、あからさまに狼狽した。
「どちらさまですか」
「株主です」。吉岡さんは筋肉と脂肪のたっぷりついた大きな体を揺らしながら、どしどしと彼らのほうに歩み寄り、大きな声を張り上げた。「社長の神崎さんはどちらですか?」
「すみません、分からないです」。社員の男が言った。
「最後に社長に会ったのはいつ?」
「えっと……」。男はもう一人の社員の目を見た。その男は黙って首を横に振った。
「覚えていません、申し訳ないです」
吉岡さんは彼らのうしろに回り込み、開いてあるPCを指差した。
「これはなんのデータなんですか?」
社員は絶望したように言った。
「……分かりません」
「うふふ!」
松原が笑い声を上げた。真っ赤な顔をして口を手で押さえている。笑ってはいけないと精一杯我慢していたが、ついに声が出てしまったのだ。私は場をごまかすために近くにあった空き缶をわざと床に落として音を立てた。
投資家陣が彼らを問い詰めるうち、どうやら事業そのものが存在していないことが判明した。
高齢者向け介護サービスという性質上、現場を直接確認しに行くことが難しく、確かに株主は誰一人として実際の事業を目にしたことはなかった。ただ定期的に報告される顧客数と売上のデータだけを見て安心していた。洗脳されているのか、騙されているのか、生気のない顔でデータを叩く不思議な2名の社員を残して、神崎は1億円とともにどこかに消えてしまった。
「神崎さんに最初から悪意があったのかどうか、そこが謎だよね」
彼らと別れた帰り際に松原は言った。「最初から事業なんてやるつもりがなくてすべてが架空の詐欺だったのか。それとも事業を大げさに説明しておいて、あとからちゃんと実態を伴わせようとしている過程で、無理になってどこかに飛んでしまったのか」
「いずれにしても、さすがにこれは悪質すぎるよ」。この事件を明らかに楽しんでいる松原と違って私は複雑な気持ちだった。「でも不思議だな。私たちの前では、いけすかないけど、けっこういい人だったのに。どうして渡辺さんを紹介してくれたんだろう」
「そこが気持ち悪いよね。僕らも何かに利用するつもりだったとか?」
「でも……」。私は、我々のことを「そんな素直なところがこのコンビの魅力なんでしょうね」と言って微笑んだときの神崎の顔を思い出していた。
この日から3日後、神崎の居場所が判明したと、渡辺さんから報告があった。神崎は妻の実家の熊本にいた。経歴詐称もしていて、東大卒、外資コンサル企業出身、などという経歴も嘘だったことが分かったという。今後は投資契約書に基づいて、全額返金をさせることとなった。たいていの場合投資契約書には、出資時の説明に虚偽があった場合は返金となるよう記載がされていて、今回のケースでも同様だった。それ以外の細かい点については、どんなに松原が聞き出そうとしても渡辺さんはお茶を濁していて釈然としなかった。恐らくできるだけ穏便な解決を図っていくのだろう。
私はその日の夜、自分の部屋のベランダから、新宿の夜景を眺めていた。権威を象徴するように凛と立つ都庁。大きな高級ホテル。まばたきをするように点滅する無数のライト。神崎も自分を変えようとしたのかもしれない、そう思った。彼は舞台の上の役者みたいに、なりたい自分を完璧に演じようとした。それはもう嘘ではなくて、役柄のほうを真実だと、彼自身信じていたのかもしれない。輝かしい経歴の自分。社会的意義のある事業を立ち上げ、1億円を調達する起業家としての自分。起業家の仲間に鋭いアドバイスを送り、投資家まで紹介する親切な自分。そして彼は、舞台から消えた。今にして思えば、「そんな素直なところがこのコンビの魅力なんでしょうね」と我々に言ったあの目は寂しそうだった。
彼が、私が、一切の演技をしないで生きられたのはいつが最後だったのだろう? 春の空、控えめに瞬く星空を見ながら、小さな男の子が泣いている姿が浮かんだ。
文/関口 舞