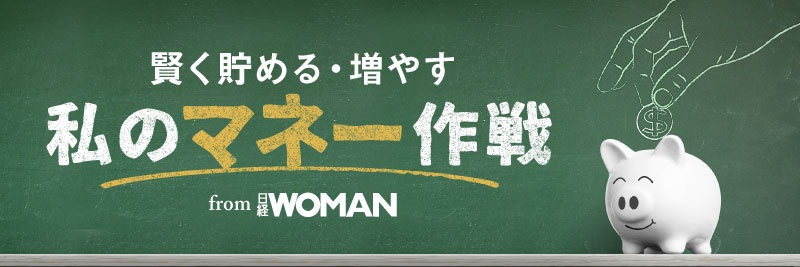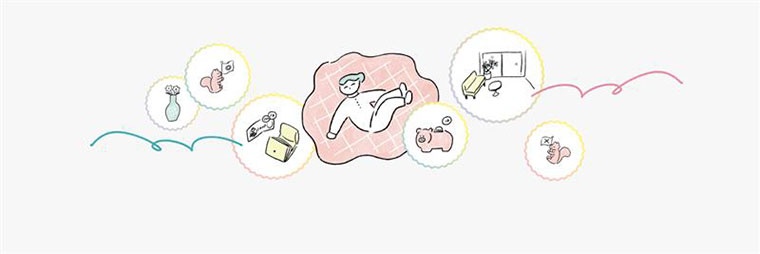これまで大きな病気やケガをしてこなかったという人も、頻繁な通院が必要になるのが、妊娠・出産のタイミングです。健康保険や自治体から分娩や健診にかかる費用の補助が出るとはいえ、出産スタイルや産院の選択肢によっては予想外に金額がかさんでしまうことも。そんなケースに備えて知っておくと安心な方法をファイナンシャルプランナーの坂本綾子さんに教えてもらいました。
家族全員の医療費が10万円を超えたら検討を
妊娠中の妊婦健診の費用のほとんどは自治体から受け取れる補助券でまかなえるため、特殊な検査をしなければ、まとまった金額をクリニックに払う必要はありません。また、連載前回の「出産っていくらかかる? 用意すべきお金をFPが指南」でもお伝えしたとおり、出産をすると誰でも1児につき42万円(多胎児は人数分)の出産育児一時金が健康保険組合や自治体から受け取れるため、産院を選ばなければ、分娩のための入院費用も抑えることができます。
ただ、通院にかかる交通費は自己負担です。また、入院費用が42万円以上かかるケースもあるため、妊娠・出産というライフイベントのあった年は医療費がかさみます。また、最近選ぶ人が増えている無痛分娩も、通常の分娩費用に加えて20万円ほどかかるため、1年で数十万単位の出費が発生することも。ただ、その場合でも、費用の一部を取り戻す方法があります。次ページからその方法についてご紹介します。